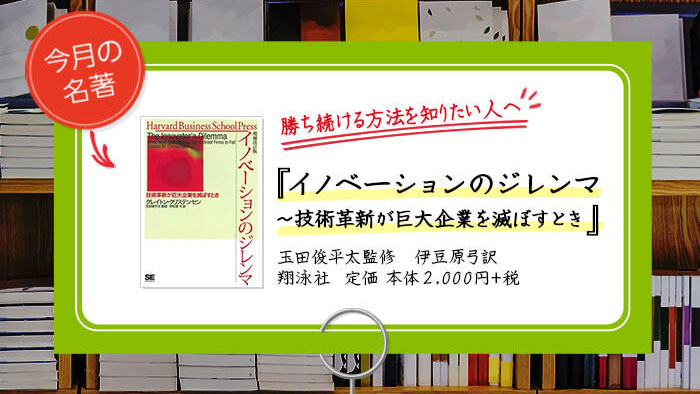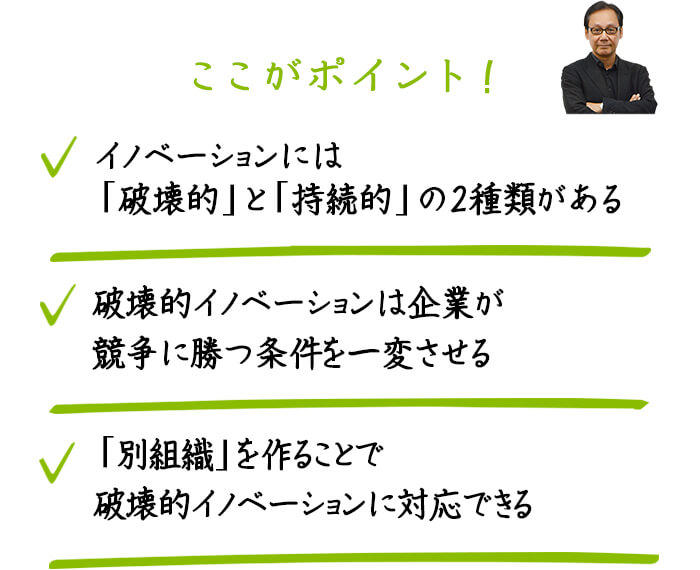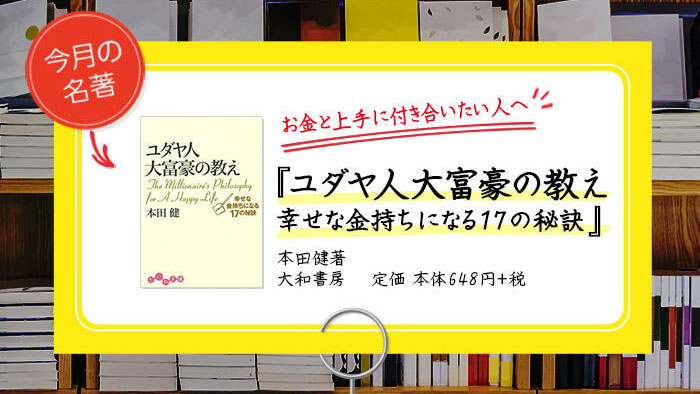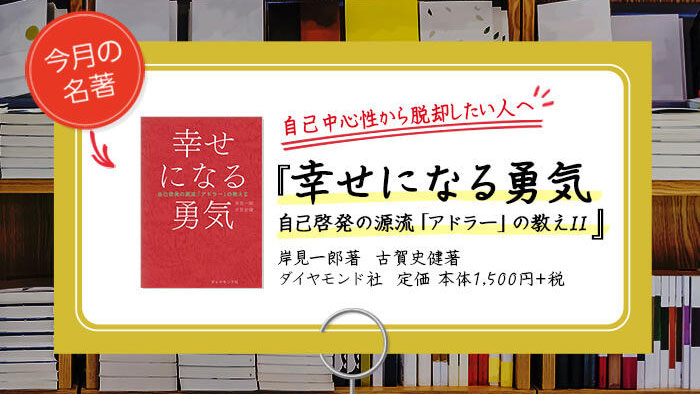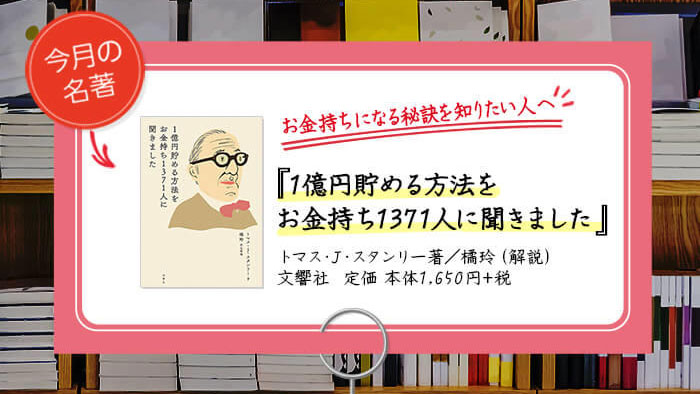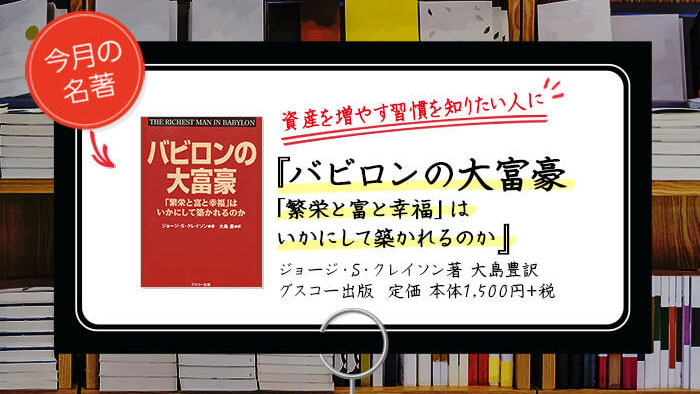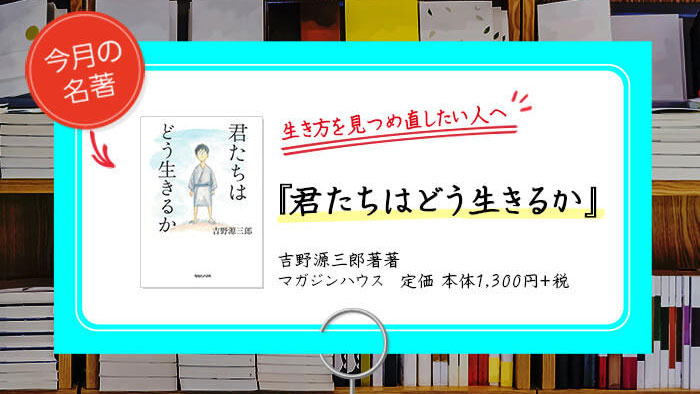イノベーションには「破壊的」と「持続的」の2種類がある
「偉大な企業はすべてを正しく行うが故に失敗する」
著者の故クレイトン・クリステンセン氏(ハーバード・ビジネス・スクール教授)が本書で提起した「イノベーションのジレンマ」の核心はこの一言にあります。
優れたマネジメント能力を持ち、顧客目線で様々な工夫を実践していた業界のトップ企業が、まさにその優れた能力故に、企業の競争条件を一変させるような「破壊的イノベーション」には対応できず業界のトップから脱落してしまう。
勝ち組企業の「強さ」がやがて「弱さ」に転化してしまうジレンマの存在を、「破壊的イノベーションの法則」として一般化した本書の価値は、20年以上たった今も全く色褪せていません。
著者は、イノベーション(技術革新)には2種類あると指摘します。
1つ目は、既存の製品の性能や使い勝手を高めるイノベーションで、著者はこれを「持続的イノベーション」と呼びます。
2つ目は、既存の製品の存在意義をいずれ失わせてしまう可能性を持った画期的なイノベーションで、著者はこれを「破壊的イノベーション」と名付けました。
たとえば、大型コンピューターの処理能力を上げる技術は「持続的イノベーション」ですが、ノートパソコンの登場は大型コンピューターにとって「破壊的イノベーション」となり、その役割を終わらせてしまいました。
破壊的イノベーションは企業が競争に勝つ条件を一変させる
では、なぜ「破壊的イノベーション」によって、優れたマネジメント能力を持つ業界のトップ企業が、その優れた能力故に敗れてしまうのでしょうか。
ごく常識的には、市場から脱落してしまうのはマネジメント能力に乏しく、顧客目線で様々な工夫を実践していなかった企業に思えます。
著者は、様々な業界での勝ち組企業の交代劇を分析しながら、ジレンマの存在を例示します。
ここでは、より分かりやすいショベルカー業界の例を紹介しましょう。
1920年代から1960年代にかけて、アメリカではケーブルでショベルを動かす機械式ショベルカーが主流でした。業界を代表するショベルカーメーカーは顧客である土木・採鉱などの掘削工事業者の要望に応え、ショベルの大型化や駆動性の向上などの「持続的イノベーション」を次々に実現し、売り上げを伸ばしていました。
その最中の1947年、英国のベンチャー企業がそれまでにない油圧式ショベルカーを開発します。容器に入れた油に圧力を加え、その反発力でショベルを動かすイノベーションを実現したのです。
しかし当初、機械式ショベルカーの顧客である掘削工事業者からは見向きもされませんでした。
油圧の力が小さいため大きなショベルを取り付けられず、土木や採鉱などの掘削工事には役に立たなかったからです。
そこで、英国のベンチャー企業や、追随して油圧式ショベルカーを手がけた企業は、掘削工事業者に代わる新たな顧客を開拓しました。小規模な住宅工事業者です。
彼らは上下水管を入れる狭い溝などを掘るために、小さなショベルの油圧式ショベルカーを購入するようになりました。
顧客を得た油圧式ショベルカーメーカーは、ショベルの大型化や駆動性の向上などを進めていきます。
そして1960年代後半から70年代にかけて、ついに機械式ショベルカーと遜色ない性能を実現しました。
この時、ショベルカーメーカーが競争に勝つための条件が変わりました。機械式ショベルカーの顧客だった掘削工事業者たちは、ショベルカーを選ぶ時、ショベルの大きさや駆動性よりも安全性、信頼性を重視するようになったのです。
機械式ショベルカーは、ケーブルが切れると最悪の場合、死亡事故にもつながりかねません。掘削工事業者たちは、機械式よりも安全で信頼性の高い油圧式を選ぶようになり、結果、機械式ショベルカーメーカーは次々に競争から脱落していきました。
主要な機械式ショベルカーメーカー30社のうち、生き残りを図ることができたのは4社に過ぎなかったのです。
ほとんどの機械式ショベルカーメーカーが油圧式に移行できなかった原因は、技術的に対応できなかったからではなく、顧客である掘削工事業者の需要にありました。
初期の油圧式ショベルカーはショベルが小さすぎて掘削工事業者から見向きもされませんでした。顧客の反応から「油圧式ショベルカーに商機はない」と判断して、油圧式ショベルカーへの開発を打ち切っていたのです。
英国のベンチャー企業などが小規模な住宅工事業者に油圧式ショベルカーを売っていたことを知っていても、敢えて参入しませんでした。
掘削工事業者に機械式ショベルカーを売る事業に比べたら、利益率がはるかに低かったからです。
機械式ショベルカーメーカーが淘汰されてしまったのは、マネジメントが悪かったからではなく、顧客の需要に真摯に耳を傾けていたからでした。
まさに「偉大な企業はすべてを正しく行うが故に失敗する」の言葉通りだったのです。
「別組織」を作ることで破壊的イノベーションに対応できる
業界のトップ企業が「破壊的イノベーション」に対応できる方法を著者は紹介します。
その一つの答えは、「別組織を作る」ことです。
著者が提案するのは、社内に別組織を設けたり、社外ベンチャーを設立したりして、それらに「破壊的イノベーション」を活用した製品の開発や新規の顧客開拓などを任せる手法です。
その際には「小さな機会や勝利にも前向きになれるような小さな組織」に任せること、「市場は試行錯誤の繰り返しの中で形成されていくものである」=新規顧客開拓には試行錯誤や失敗が付きものであると経営者が認識することがポイントだと指摘します。
著者が提案した手法は今日、多くの大企業が取り入れています。
たとえば、自動車業界のトップクラス企業・トヨタ自動車は、自動車業界にとって「破壊的イノベーション」になりかねないAI(人工知能)による自動運転に対応するため、2016年1月、アメリカのシリコンバレーにAIの研究所である「トヨタ・リサーチ・インスティテュート」を設立し、同年3月には自動運転技術を手がけるアメリカのベンチャー企業ジェイブリッジ・ロボティクスの人員をスカウトしました。
著者のクリステンセン氏は2020年1月に亡くなりました。
しかし、彼が提起した「破壊的イノベーションの法則」「別組織による破壊的イノベーションへの対応」は、今も企業経営の主要な課題として生き続けています。
渋谷和宏のコレだけ覚えて
イノベーションのジレンマから学べる「分散投資」の大切さ
本書『イノベーションのジレンマ』は、優れた技術とマネジメント能力を持ち、業界をリードしていた企業が、その優れた技術とマネジメント能力ゆえに業界での優位性を失ってしまうジレンマの存在を浮き彫りにし、「破壊的イノベーションの法則」として呈示しています。
さらに、ショベルカー市場での勝ち組企業の交代劇を通して、破壊的イノベーションによる競争条件の変化がいつ起こるのか、市場で支配的な地位を得ている業界のトップ企業でさえ予測しがたい事実を明らかにしました。
これらの法則や事実は、お金を運用する側にとっては、業界のトップ企業だけに投資することのリスクを示唆しています。
本書が示しているように、破壊的イノベーションを起こす企業には新興のベンチャー企業や中堅企業が少なくありません。中にはスタートアップ企業が破壊的イノベーションを武器に一気にトップ企業へと駆け上がっていくことさえあります。
だとすれば、お金を運用する側は長期の視点に立ち、トップ企業、大企業だけでなく新興のベンチャー企業や中堅企業や中長企業にも目配りをするべきでしょう。
日本企業だけでなく新興国も含めた外国の企業に分散投資することが、リスク分散につながることもあるはずです。
本書は、運用の基本は長期の視点に立った分散投資であることを改めて認識できる1冊でもあります。
-
※
2020年3月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。